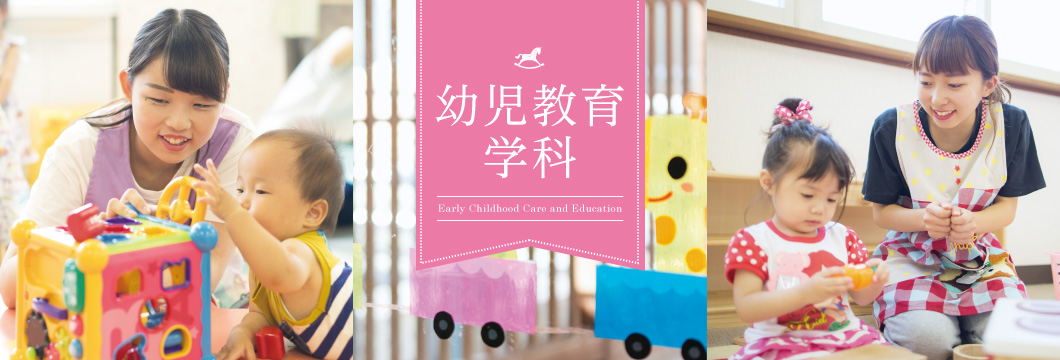教員紹介
専任教員
学科長・教授光井 恵子

Comments
子どもの生活の周りには音楽があふれています。子どもの音楽的表現の育ちに、保育者としてどのように関わっていけばよいのでしょうか。音楽の基礎技能を身に付けながら、様々な授業を通して感性を磨き、創造性を高めながら一緒に学んでいきましょう。
研究分野
ピアノ教育、音楽表現
教授川島 民子

Comments
どんな子どもたちも、大人が思っている以上に秘めた力と可能性をもっています。それは、ちょっと気になる子どもたちも一緒です。一人ひとりの子どもたちの思いや願いを汲み取り、その思いや願いを中心としながら、子どもたちが持っている力を存分に引き出せる、そんな保育者を目指して一緒に学んでいきましょう。
研究分野
特別支援教育、発達性協調運動障害
教授茂木 七香

Comments
メッセージはこちら
准教授大橋 淳子

Comments
様々な影響を受けて育っていく子どもたち。自らが興味・関心をもって関わりたくなる環境を用意することの重要性や主体的・対話的で学びを促す援助について考えていきましょう。そして、つぶやきや豊かな発想に気付き、捉えられる保育者をめざし、季節の変化や社会の動きを敏感に感じられる自分でいられるように、また、ワクワクの気持ちを忘れないで保育の引き出しがたくさんある魅力ある保育者について一緒に学んでいきましょう。
研究分野
保育環境、教職実践演習
准教授垣添 忠厚

Comments
子どもの心身の成長に、運動は欠かせない要素です。乳幼児期においては、目に映る新しい世界に興味をもち、触ってみたい、やってみたいという欲求によって、自然と体を動かした結果が丈夫な体づくりとなります。また、親子や保育者など大人との遊びを通して体を触れ合いながら楽しさ共有することが、心の成長の支えになります。身体や運動機能の発達は個人差により様々ですが、生涯にわたる健康づくりの礎として、子どもたちが体を動かすことが楽しいと思える育て方がなにより重要だと考えています。
研究分野
幼児体育、特別支援教育、発達障害児者支援、障がい者スポーツ
講師岡本 英通

Comments
準備中
研究分野
準備中
講師立崎 博則

Comments
好きなものを見つける、好きなものについて語る、好きなものを増やす。表現の初期段階で重要なのはそんな感性についての心の動きです。よく見て、手を動かし、自分の「好き」増やし、子どもたちのたくさんの「好き」を引き出すことを目標にしてみてください。
研究分野
幼児美術、造形ワークショップ、現代アート、彫刻
講師名和 孝浩

Comments
子どもの生活の中心には、いつも遊びがあります。その遊びを通して子どもは人やモノ、自然と出会い、心豊かに育ってゆきます。そして、そこには子どもの思いに寄り添い、共に歩む保育者の専門性が隠されています。保育者として、子どもをまるごと受け止め、育ちを支える援助の方法とはどのようなものか。実践的なエピソードや実習を通して、保育の総合的な力を一緒に育てていきましょう。
研究分野
乳児保育
講師宮本 絢子

Comments
皆さんにとって保育園や幼稚園の先生は、どのようなイメージでしょうか?何でも器用にできるイメージから向き不向きがあると思われがちですが、子どもたちは自分の思いに寄り添ってくれる保育者、一緒に楽しんだり考えたりしてくれる保育者を求めています。この3年間で、得意なことを伸ばして得意でないことにもチャレンジしながら、保育の引き出しを増やし、子どもや保護者、同僚の保育者の多様性を認め合える保育者を志してほしいです。幼少期にどんな先生に出会って、どんな保育に出会ったかということが、子どもたちの人生に影響を与える保育・幼児教育の仕事は本当に大切で素敵です。皆さんが卒業して社会人になった時、何より子どもに関わる仕事に携わってよかったなと心から思えるようにサポートしていきたいと思います。
研究分野
こども学、保育学、保育者養成、保育士の業務負担軽減と離職防止
客員教授
客員教授佐藤 弘道

Comments
子どもたちは「あそび」を通じてたくさんの学びをします。そして、体験と経験を繰り返し「動きつくり・体つくり」、さらに「仲間つくり」をします。そのサポートの仕方を一緒に学んでいきましょう。運動あそびの目的や補助や声掛け、子どもと向き合うポイントなど、現場で役立つヒントをつかんでください。
研究分野
運動あそび、親子体操、健康体操
佐藤先生の著書を含む保育の教材資料のご紹介
ほいくとかいごのおかいもの(株式会社世界文化ワンダー販売)
非常勤講師
| 浅井 佳士 | 今村 民子 | 遠渡 絹代 | 小川 寿実子 |
| 春日 有貴江 | 加藤 有子 | 川村 香織 | 神谷 俊介 |
| 後藤 恵子 | 佐々 智美 | 竹内 美樹 | 野々垣 行恵 |
| 日比 千穂 | 日比 裕美子 | 松岡 邦明 |